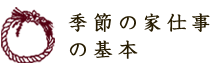

お正月料理 おせち・お雑煮


お雑煮とは、年神様に供える食材を雑多に煮たもの。
元々は、元日の朝に汲んだ「若水(※)」で煮ていました。
お雑煮をいただくことは、
神様と一緒に食事をする儀式として大切にされています。
地域によって味付けや食材が異なるのも、面白いところ。
大きく分けると、関東や九州、中国地方は、醤油ベースのすまし仕立て、
関西は白味噌仕立てが基本です。
※若水(わかみず):元日の朝、年が明けて最初に井戸から汲んだ水のこと。
おすすめのお雑煮レシピ
地域の垣根を越えて、楽しんでいただけるようなレシピをご紹介。
お正月の時期に嬉しい栄養素を含んでいるので、
いつものお雑煮の代わりに、
または正月の後半に余ったお餅でつくってみてくださいね。
-
けんちん雑煮

けんちん汁にお餅を入れて、具沢山のお雑煮に。
たくさんの野菜を一度に摂れるので、正月の野菜不足解消に最適です。
また、根菜で食物繊維もたっぷり補給。材料(2人前)
里芋 50g(中1個)
大根 50g(2㎝)
人参 30g(1/6個)
ごぼう 30g(1/5本)
ねぎ 30g(1/3本)
しめじ 50g(1/4パック)
豚肉 40g
綿豆腐 60g(1/5丁)
ごま油 大さじ1/2
餅 3個
味噌 小さじ4
だし汁 500cc強
小ねぎ 少々
つくり方
-
1. 食材を用意します。里芋は、皮をむき半月切りにします。人参、大根は皮をむき、イチョウ切りにします。ごぼうは、斜めに薄く切ります。しめじは、石つきを除き、ほぐします。ねぎは、小口に切ります。豚肉は、一口大に切ります。
-
2. 鍋にごま油をひき熱し、豚肉を炒めます。肉の色が変わってきたら、1の野菜を炒め合わせます。豆腐を入れて、つぶしながらさらに炒めます。
-
3. だし汁を加えて煮ます。沸騰したらアクをとり、弱火にして2~3分煮ます。
-
4. 餅は半分に切り、焼いておきます。
-
5. 3に味噌を溶き入れ、焼き立ての4を入れます。
-
6. 器に盛り付け、小ねぎを散らしたら完成です。
鶏肉と小松菜のさっぱり雑煮

干ししいたけと鶏肉の旨味を活かし、醤油ベースでさっぱりと味付け。不足しがちなビタミンを小松菜で補います。干ししいたけで噛みごたえもプラス。とろみをつけているので、お腹も満たされます。
材料(2人前)
鶏肉(胸肉) 120g
小松菜 120g(1/2束)
干ししいたけ 3枚
生姜おろし 少々
片栗粉 小さじ1
醤油 大さじ1/2
塩 少々
餅 3個
つくり方
-
1. 鶏肉は一口大に切ります。小松菜は、茹でて2cm幅に切ります。干ししいたけは湯1カップで戻し、石つきをとり、半分に切ります。
-
2. 鍋に水1カップ半と、干ししいたけの戻し汁を入れます。戻した干ししいたけ、おろし生姜、鶏肉を加えて火にかけます。沸騰してきたら、アクを取り除き、弱火にして5~6分煮ます。
-
3. 小松菜を加えてひと煮立ちさせたら、倍量の水で溶いた片栗粉を加えて、とろみをつけます。しょうゆ、塩で味をつけます。
-
4. 餅は半分に切り、焼いておきます。
-
5. 焼いた餅を器に入れて、4を盛り付けたら完成。
鮭のみぞれ雑煮

大根おろしが、正月で疲れた胃を優しく助けてくれます。また大根に含まれる消化酵素「アミラーゼ」が、お餅の消化を促す効果も。ブロッコリーと人参でビタミン補給もぬかりなく。
材料(2人前)
鮭の切り身 120g
片栗粉 少々
生姜おろし 少々
大根 200g(6cm)
ブロッコリー 60g(1/4株)
人参 40g(中1/6本)
味噌 大さじ1
餅 3個
だし汁 500cc
つくり方
-
1. 鮭は2~3cmくらいの大きさに切り、おろした生姜をまぶします。
-
2. 大根は、おろします。人参は薄い半月切りに。ブロッコリーは、小房に分けて茹でます。
-
3. 鍋にだし汁と人参を入れて火にかけます。沸騰したら、片栗粉を薄くつけた鮭を加えて煮ます。沸騰したら、弱火にして1~2分煮ます。
-
4. 餅は半分に切り、湯で煮て柔らかくします。
-
5. 3にブロッコリーを加え、味噌を溶き入れます。最後におろした大根を加えて、ひと煮立ちさせます。
-
6. 器に4の餅を入れ、5を盛り付けたら完成。
豆知識
お餅の食べ過ぎを防ぐには、お雑煮全体を食べ応えのあるものにすること。 おせちをつくるときに余った野菜などを入れて、具沢山で噛み応えのあるお雑煮にしたり、片栗粉でとろみをつけて仕上げたりすると、満足感が増しますよ。
おすすめの器
お雑煮は神様と一緒にいただく料理ですから、ちょっといい器を用意したいもの。
美しく、口当たりの優しさも魅力的な、漆のお椀はいかがでしょうか。
ぜひお正月の機会にお迎えして、毎日の暮らしでも使ってみてください。
-
上品な佇まいは、ハレの日にもぴったり。大きめなので、具沢山のお雑煮もしっかり受け止めます。
-
傷が付きにくい「蒔地(まきじ)技法」仕上げなので、金属のカトラリーだって使えます。マットな質感が魅力。
-
ヘラの模様が螺旋を描くデザイン。使うほどに艶を増し、経年変化を楽しめます。
※参考文献:「和ごよみと四季の暮らし」新谷尚紀監修(日本文芸社) -






