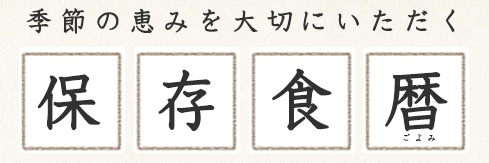
2020年4月公開
独特な香りと苦味が後を引く、ふき。
日本に自生する山菜の一つで、
アクが強く下処理に手間がかかるイメージがありますが、
近年の栽培物の多くはアクが少なめ。
皮を剥いて数分茹でるだけと、下ごしらえも手軽です。
しょうゆとみりんで煮詰める「きゃらぶき」を、
料理研究家・牧田敬子さんに教わりました。
砂糖を使わずみりんだけで仕上げるあっさりした「きゃらぶき」は、
ふきの香りや瑞々しさはそのままに、苦味がほどよくやわらいで
箸休めとしてそのままパクパクと食べられてしまいます。
アレンジレシピは、
鶏肉と一緒にふわふわの卵でとじる「きゃらぶきと鶏肉の卵小丼」と、
オリーブオイルと黒胡椒を効かせた洋風な味わいの「きゃらぶき冷や奴」です。

日本に自生する山菜の一つ、ふき
ふきは、花蕾(からい)であるふきのとうの
葉の部分に当たります。
長く伸びている部分は茎ではなく葉柄(ようへい)で、
円形に広がった葉身(ようしん)と地下茎を結びます。
花と葉は別々に育ち、ふきが出てくるのは
初春に土から顔を出すふきのとうより遅く、
春から初夏が旬になります。
成分のほとんどは水分ですが、食物繊維が豊富。
葉が青々とし、茎にツヤと張りのあるものが新鮮です。

教えていただいたのは…
料理研究家 牧田敬子さん
フードスタイリストのアシスタントとしてCMや映画などの器スタイリングや料理制作に携わった後、料理研究家のアシスタントを経て独立。雑誌や広告など、食にまつわる分野で活動。著書に「主人が痩せた!ノンオイルサラダと、野菜のかさ増しで」(文化出版局)、「ひとつの素材があれば」(家の光協会)、「すっぴん和食レシピ」(文化出版局)など。

材料(つくりやすい分量/
完成量約220g)
- ふき…1mの長さのもの5本
(葉身を除き300g) - ごま油…小さじ1
- みりん…大さじ2
- しょうゆ…大さじ1
- 出汁用昆布…5cm角1枚
- 水…200ml
(A)

1.ふきは、葉柄の太い方から包丁を使って皮を面状にめくり、皮を手でまとめて持って一気に端まで剥きます。4~5cmの長さに切ります。
【ポイント】
ふきのアクで指先が黒くなった場合は、レモンや酢をつけると落ちやすくなります。

2.鍋に1を入れて水(分量外)をひたひたに加え、中火にかけます。沸騰したら、表面がふつふつする程度の火加減にし、5分ほど茹でます。ざるに上げて水ですすぎ、水気を切ります。

3.鍋にごま油を引き、ふきを中火で炒めます。全体に油が回ったら、(A)を加えます。全体がふつふつする程度の火加減で、ときどき全体を返しながら15分ほど煮ます。
【ポイント】
砂糖を使わずみりんで調味することで、甘過ぎずすっきりした甘味のきゃらぶきに仕上がります。

4.水分がほぼなくなってきたら、火を強め、鍋をゆすりながら水分をしっかり飛ばします。バットに移して冷まし、保存容器に入れて冷蔵庫へ。冷蔵で2週間保存が可能です。
【ポイント】
1週間ほどして水っぽくなってきたら、再度火にかけて乾煎りし水気を飛ばすと、味が締まります。

「きゃらぶき」を鶏肉と一緒に卵とじに。
鶏肉と卵のやさしい味わいを、「きゃらぶき」の香りと苦味が引き締めます。
とじる卵とは別に生の卵黄をのせることで、より濃厚な味わいに。
飯碗でいただく小丼サイズですが、しっかりボリュームのある一品です。
「きゃらぶき」をつくる際に使った出汁用昆布も、細く切って箸休めにどうぞ。
材料(1人分)
- 「きゃらぶき」…20g
- 鶏もも肉…50g
- 水…50ml
- みりん…小さじ2
- しょうゆ…小さじ1
- 卵…2個
- ごはん…1/2合分
- 青のり…適宜
つくり方
1. 鶏肉を1~1.5cm角に切ります。
2. 卵1個分の黄身と白身を分けておきます。ボウルに残りの卵1個分を割り入れ、分けておいた白身を加えて溶きほぐします。黄身は仕上げに使います。
3. 小鍋に水を入れて沸騰させ、みりんとしょうゆを加えます。鶏肉を加えて火を通します。
4. 2の溶き卵を回し入れて「きゃらぶき」をのせ、卵が半熟になるまで火を通します。
5. 器にごはんをよそい、4をのせて卵黄を落とし、青のりを散らします。
牧田さんが選んだ器は…
平茶わん ST-20(白山陶器)
広い口と浅めのかたちが特徴的な飯碗。「上に具をのせるので、口径は広い方がいいなと思いました。これは、大きすぎず浅いので、食べやすいかたちですね。白地に藍色の模様が施され、料理が美味しそうに見えます」
これからの季節食卓に登場する頻度が増える冷や奴。
「きゃらぶき」を刻んだものをのせ、オリーブオイルと黒胡椒を振れば、
ぐっとおしゃれで洋風に。
香りの強いオリーブオイルは、ふきとの相性抜群。
お互いを引き立て合い、香り高い上品な一品になります。
材料(1人分)
- 「きゃらぶき」…15g
- 絹ごし豆腐…1/4丁
- 塩…ひとつまみ
- オリーブオイル…小さじ1
- 粗びき黒胡椒…少々
つくり方
1. 「きゃらぶき」を5mmの長さに切ります。
2. 絹ごし豆腐を器に盛り、塩を振って下味をつけます。
3. 1をのせてオリーブオイルを回しかけ、粗びき黒胡椒を散らします。
牧田さんが選んだ器は…
小皿 和文・赤 籠目文
(バーバー/BARBAR)
昔から永く愛されてきた和の文様をあでやかな赤色で描いた小皿。「『きゃらぶき』と豆腐だけだと地味になってしまうので、お皿に赤を入れて全体の印象を華やかにしてみました。家庭料理の場合、凝った盛りつけをしなくても、お皿に柄があるとそれだけで料理が映えるんですよね。文様の籠目も涼やかでこれからの季節にぴったり」















