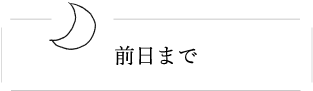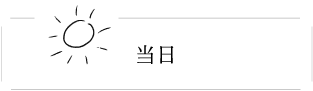1日をごきげんにはじめる!仕込み上手な朝ごはん
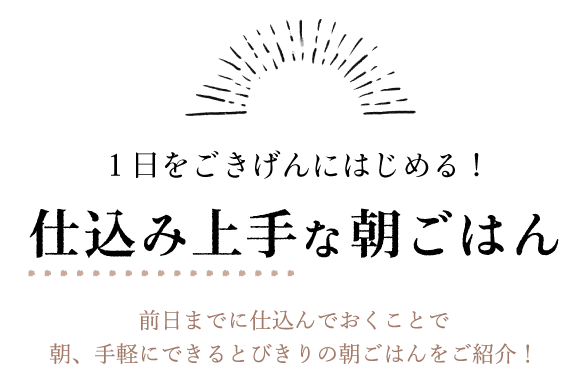

2023年4月公開
体をやさしく温め
軽やかに整える
瀬尾幸子さんに教わる
「白粥」
軽やかに整える
瀬尾幸子さんに教わる
「白粥」
重たい朝ごはんだと眠気を招いたり、昼休みに食欲が湧かない……なんてこともあるので、
朝はお粥派という料理研究家の瀬尾幸子(せお ゆきこ)さん。
起き抜けの体をやさしく温めて、寝ている間に失った水分も補えるから、
1日をいいコンディションではじめられるのだとか。
手軽に美味しくできる家庭料理を発信されている瀬尾さんに、
前日仕込むことで簡単につくれる「白粥」と、
それにぴったりな「海苔の佃煮」、「ねぎ味噌」、「練り梅」の3種のお供を教わりました。
沸かしたお湯にご飯を入れて一晩置くだけで、翌朝には白粥のでき上がり。
つくりおきしておいたお供をのせれば、お粥を食べる手が止まらなくなること請け合いです。
教えていただいたのは……
料理研究家
瀬尾幸子さん

「手抜き」ではなく「知恵を絞る」ことを大切に、誰でも手軽に美味しくできて、毎日食べ続けることのできるシンプルなレシピを提案。
TVや雑誌などのメディアへのレシピ提供、食品メーカーの料理開発などで活躍中。
料理レシピ本大賞 in Japan受賞の「ラクうま」シリーズをはじめとして、「おつまみ横丁」シリーズ、「おかず食堂 ごはんがすすむ」など、著書多数。
近著は「ラクなのに絶品!のっけごはん&のっけパン170」。
白粥

生米から炊くのではなく、沸かしたお湯に炊いたご飯を入れて一晩寝かせるだけ。
朝は温めればすぐに食べられる簡単お粥。
気温が上がってきても、朝晩の気温差や冷房などで体は冷えやすいもの。
朝からお粥をいただいて体を温めれば、不調知らずの1日をはじめられそうです。
ご飯の約4倍の重さの水でふやかすので、お粥1人前で、ご飯の量は約半膳分。
糖質が気になる人にもうれしいですね。
お湯の代わりにほうじ茶でつくればほうじ茶粥。
朝温めるときに溶き卵を入れれば玉子粥と、アレンジもできるので、
いろいろなお粥をお楽しみください。
仕込み上手のポイント
前日に約4倍の重さの沸かしたお湯にご飯を入れ、蓋をしてふやかしておけば、
長時間炊かなくてもほどよいやわらかさのお粥に仕上がります。
土鍋やステンレス製の鍋など、保温力のある鍋がおすすめです。
材料(2人分)
- ご飯…1膳分(150g)
- お湯…600ml
つくり方

鍋でお湯を沸かします。
ご飯を入れて蓋をして再沸騰し、蓋をして一晩置きます。

温めなおして完成です。
グツグツさせすぎないようにするのが、さらりとしたお粥に仕上げるコツです。
電子レンジが使用可能な土鍋なら、電子レンジで温めてもOKです。
海苔の佃煮

お粥はもちろん、ご飯のお供としても定番の海苔の佃煮は、
手づくりすると、市販品よりも塩分や甘さも控えめで、
海苔本来の風味がしっかり感じられる仕上がりに。
手頃な海苔や、少ししけってしまった海苔の活用法としてもおすすめです。
材料(つくりやすい分量)
- 海苔(全形)…10枚
- しょうゆ…大さじ6
- 砂糖…100~120g
つくり方

海苔を2cm角程度の大きさに細かくちぎって、一晩水に浸けてふやかしておきます。

翌日、鍋に海苔、しょうゆ、砂糖を入れて強火にかけ、焦げつかないよう時々ヘラでかき混ぜます。
煮立ったら、ブクブクが続く中火程度の火加減に弱めます。
ヘラで鍋の底をなでると、写真のように底が見えるくらいのかたさになったら火を止めます。冷めるとかたくなるので、少しゆるいくらいで火を止めます。

熱いうちに瓶に入れて蓋をし、蓋も消毒するため裏返します。
冷蔵庫で約2ヵ月保存可能です。
ねぎ味噌

味噌に刻んだ長ねぎとかつお節を混ぜたおかず味噌。
火を通さないので、味噌の風味はそのままに、長ねぎのシャキシャキとした歯応えも
アクセントになっています。
お湯を注げば即席味噌汁にもなり、お弁当にもおすすめ。
材料(つくりやすい分量)
つくり方

長ねぎを、2mmくらいの薄さの小口切りにします。
青い部分もかたくなければ使って大丈夫です。
長ねぎ、味噌、かつお節を、具材が偏らないように混ぜます。
1時間置けばねぎがしんなりして食べやすくなります。
冷蔵庫で約2ヵ月保存可能です。
練り梅

食欲をわかせ、朝の寝ぼけた体にも酸っぱい目覚めをくれる梅干し。
種をたたいた練り梅は、トロリとしたお粥と一緒に食べやすくておすすめ。
毎回種を取るのはおっくうなので、時間のあるときにまとめて練り梅にしておけば、
お供としてだけでなく、調理のときに手軽に使えます。
残った種も無駄にしない「梅汁」のつくり方も教えてもらいました。
材料(つくりやすい分量)
- 梅干し…11粒(240g)
- (梅汁をつくる場合)水…1カップ強
つくり方

種の部分を揉むようにして梅干しから種を取り出し、包丁で刻みます。

瓶などに入れ、冷蔵庫で約2ヵ月保存可能です。
(梅汁をつくる場合)
取り出した種を小鍋に入れ、水を加えて煮ます。
途中、果肉をつついて溶かします。
煮立ったら、ザルで濾します。
冷蔵庫で保管してください。
梅味調味料として、梅酢のように野菜にかけたり、焼酎で割って飲んだりするのもおすすめです。
冷蔵庫で約2ヵ月保存可能です。
瀬尾さんの器選び

白粥を引き立たせるお碗を主役に、爽やかな青や白も添えて、朝らしさのある雰囲気に。
白粥のお碗は、熱くなるので持ちやすい高台のあるものを。大きさ、深さがちょうどよくて、締まりのある飴色も白粥を引き立ててくれます。
青や白の小皿は食材が引き立つ色で、清々しい印象にしてくれます。
レンゲは全体に馴染むアイボリーを選びました。
お盆はお碗と同系色で落ち着きのあるものを、クロスは控えめな柄で全体を邪魔せず、
朝らしい軽やかな色のものを合わせました。