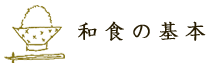
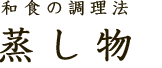
和食の調理法 蒸し物

水蒸気で食材を加熱することで、ふっくらと仕上げる蒸し料理。
茹で物のようにビタミンCなど水溶性の栄養素が溶け出しにくいうえ、
炒め物のように油を必要としないのでヘルシーに仕上がります。
蒸し物はアクが溶け出しづらいため、アクが少ない食材が適しています。
今回は常備菜として人気の蒸し鶏を例に紹介します。
鶏肉は加熱しすぎるとパサつきやすいので、
加熱時間には注意が必要です。
蒸し鶏
材料
鶏むね肉:1枚(250g)
塩(塩もみ用):1g ※鶏むね肉の0.5%
ねぎ(青い部分):1/5本分
生姜スライス:少々
酒:大さじ1
-

1
フォークなどを使って皮に穴を空けます。
point
皮に穴をあけることで味が染み込みやすくなるほか、蒸したときの皮の縮みを防ぐことができます。触ってみてかたいところを中心に、3~4ヵ所刺しましょう。
-

2
耐熱皿にのせて、塩を両面に振りかけます。
point
塩を振ることで、加熱後も肉独特の弾力を保持でき旨味も増します。
また肉の場合は蒸し汁を残したいので、下に耐熱皿を敷いて蒸します。 -

3
塩を全体にもみ込みます。
-

4
ざく切りにしたねぎとしょうがをのせて、酒を振りかけます。
point
ねぎ、しょうが、酒はくさみを取るために入れます。
-

5
湯を沸かし、しっかり蒸気が上がった状態の鍋に蒸し板を入れて、耐熱皿ごと鶏肉を置きます。蓋をして15~20分ほど強火で蒸します。
point
強火で短時間で蒸すとくさみが少なく、弱火で時間をかけて蒸すと身がふっくらと仕上がります。お好みで火加減や時間を調節してください。
-

6
鶏肉に竹串などを刺して透明の汁が出てきたら、火が通っている証拠です。蒸し汁に浸けたままの状態で冷まします。
point
蒸し汁に浸けたまま冷ますとしっとりと仕上がります。蒸し汁は鶏の旨味が詰まっているので、スープなどに活用しても。
-

6
冷めてから食べやすい大きさに切り分けます。
豆知識
肉だけでなく野菜や魚を蒸すときも、しっかりと蒸気が上がった状態で材料を蒸し器に入れるのがポイント。蒸気が十分に上がらず温度が低い状態で食材を入れると、水っぽい仕上がりになるうえ、蒸し時間がかかり旨味や栄養が流出してしまいます。
おすすめの道具
蒸し物をするなら、道具選びが重要。
熱伝導がよく蒸し上がりがはやい金属製のスチーマー。
蒸気の抜けがいいから、
べちゃっとした仕上がりになりにくい木製のせいろ。
遠赤外線効果でじっくり中まで熱し、ふっくらと仕上げる陶製の土鍋。
迷ったら、まずは手持ちの鍋に入れて使う
蒸し器や蒸し板からはじめてみるのも一つです。
-
これ一つで蒸し物ができるコンパクトな蒸し器。金属製は熱伝導がいいので蒸し上がりがはやいうえ、洗いやすいので肉や魚を蒸すにも最適です。
-
香りのいい木曽ヒノキを贅沢に使ったせいろ。直径「24cm」と「27cm」と大きめのサイズ展開なので、たっぷり蒸したい人にもおすすめ。
-
横浜中華街でプロの愛用者も多い「照宝」のせいろ。身と蓋がずれにくいよう溝があり、日本のヒノキを桜の樹皮で留めたcotogotoオリジナル仕様です。
-
蒸し物用のすのこがついた土鍋。蓄熱性が高い伊賀土と遠赤外線の効果が高い釉薬が使われているから、食材の芯までじっくり熱を伝えて美味しく仕上がります。
-
まず蒸し料理をはじめてみたいという人には、手持ちの鍋に入れて使う「蒸し板」や「蒸し器」を。「蒸し板」は鍋のサイズに合わせて選んでください。
※参考文献:「調理に必要なデータがわかる 下ごしらえと調理のコツ 便利帳(成美堂出版)」










